最後にもういちど、
伝えたいことがあるんだ。
真実は一つとは限らない。
〜山崎退の場合〜
いつだって、
君は俺のお姫様で。
自分が王子様になれないことは分かっていたけれど、
ピンチの時に力になってあげられる騎士(ナイト)のつもりではいたんだよ。
でも、それも思い上がりだったんだって、
目の前の君の瞳が、飛び散った赤い光を反射するのを見て、
思い知らされた。
何でこんなところに、なんてバカバカしい話。
今日の取り物の現場は君の買い出しの通り道。
こんな大事な事に、誰も気づかなかったなんて。
間に合え、間に合え、と伸ばした手が君に届く一瞬前に、君の体が跳ねた。
喉の少し下のあたりから、真っ赤な華が咲いたみたいに。
俺が伸ばした手をするりとかわして、君は俺の胸の中にぽすり、と倒れ込んだ。
伸ばした手を引っ込めることも出来ないまま、俺は小さく震えながら立ちすくむ。
どく、どく、と脈打っているのは俺の心臓だろうか?
それとも、生ぬるく腹を湿らす君の赤?
ずるり、
布の上を肌が滑る音が、これほどまでに嫌なものだとは思わなかった。
動けずにただ突っ立っているだけの俺の胸から、君の頭が体ごと滑って、崩れ落ちる。
崩れて、落ちた。
「・・・・・」
伊達にこの世界で生きていない。
どう見ても致命傷。
「・・・、ちゃん・・」
てんで言う事を聞かない体をなんとか動かして、倒れた君の体を抱き起こす。
君は、もう二度と動かない。
「う」
「うわああああああああああ」
かくんとのけぞるように、力なくたれた君の頭。
口の端から一筋赤い線が垂れて、
まるで笑っているように見えた。
〜沖田総悟の場合〜
姉さんが倒れた。
病名を聞かされた時は、本気で医者を切り殺そうかと思った。
なんて偶然?運命?はは、笑えねえ。
彼女の病は、死んでしまった自分の姉と同じ病名だった。
その日からまともに寝れなくなった。
迷惑だと分かっていても、染つるからと嫌がられても、ずっとそばにいた。
染つればいい、染つればいい。
だって、それは、その病気は。
・・・おれがもらって生まれて来るはずだったのに・・っ、
彼女は姉上よりもずっと発症が遅い。幼いころから発症してた姉上も25まで生きた。
直ぐ死ぬわけじゃない。それでも、
「最初」から「最後」までを知っている「自分」にはその時間すらもカウントダウンに見えた。
なにも出来ずに、一日、また一日、過ぎて行く。
かみさま、かみさま、お願い。
何でもするから。コイツだけは。この人だけは、
・・連れて行かないで。
彼女は・・・・、俺の目の下に出来たくまを笑い、
病人より食欲ないってどういうことですか、と怒り、
「大丈夫」と優しく微笑んで頭を撫でてくれた。
『あの人』と全くおんなじ、『いなくなる人の顔』で。
そんなある日、その日の討入りでヘマをして結構深い傷を作って帰ってきた俺を見て、姉さんは物凄く傷ついた顔をした。
傷をしたのは俺の方なのに。
その時は彼女がどうしてそんなに悲しそうな顔をして抱きしめてくれるのか、俺には分からなかった。
酷いめまいと吐き気がしてよろめいた体を、後ろにいた男が黙って片手で支えてくれる。
怪我してるんだから、今日くらい自分のお部屋で寝なさい?なんて言われた次の日、
姉さんは一人冷たくなっていた。
『お休み、そーくん』
昨日の夜交わした最後の言葉がよみがえる。彼女の手には小さな瓶。
俺は相当動転してたんだと思う。
衝動的に彼女の手からその瓶を取り上げて飲もうとするくらいに。
でも、口を付ける前に伸びてきた腕によって瓶は取りあげられる。
とんでもなく馬鹿な事を考えた俺よりも、一瞬だけ、更に馬鹿になっちまった奴がいたんだ。
隣に。
好きでたまらなかった娘と、俺にとっては大事な馬鹿が、ピクリとも動かず眠っている。
そんな彼らの隣で動けずにいる俺は、今日も吐き気がするくらい健康だ。
〜土方十四郎の場合〜
彼女は大切な人でした。
狂ってしまった自分に嫌な顔一つせず、
寧ろ幸せそうに付き合ってくれる彼女が。
いつからだっただろう。コレが始まったのは。
一人になりたくなる。そのくせそれが怖ろしいと思う。
不安で仕方なくなる。それなのに何が不安なのか分からない。
人を傷つけたくなる。見ず知らずの相手じゃない、もっと・・・自分に近い者を。
人間の性質とは複雑なもので、えてして全くの矛盾も簡単にあり得てしまう。
自分が傷つかないように他人を傷つける。
他人が傷つかないように自分を傷つける。
周りの期待があるからこそ能力が発揮できるなんて奴は、
その実他人からの期待に答えようとするあまり自分を犠牲にする。
一人じゃ何もできないくせに、一人でなくては生きられないのだ。
「私、殴られたいんです」
そう言ってにっこりほほ笑んだ娘は、頭を撫でてやればくすぐったそうに喉を鳴らす。
「殴ってください」
彼女は殴られても笑顔だった。
驚くことに、彼女には俺の不安が何なのか分かっているようだった。
そして彼女を殴ることで、俺の心は驚くほど平穏を取り戻す。
何度こんなことを繰り返したのだろう。
波がひいた後、いちいち苦悩する事もなくなった。
叩かれても、殴られても、首を絞められても、彼女は笑顔でこう言ってくれた。
「私は貴方の味方です」
「ありがとう」
彼女は大切な人でした。
だんだんエスカレートしていく自分に嫌な顔一つせず、
寧ろ幸せそうに付き合ってくれた彼女が。
今俺の腕の中で、静かに冷たくなっていく。
〜坂田銀時の場合〜
自分だけの君が欲しくて、君を攫ってきました。
まず、勝手に帰らないように鎖でつなぎました。
騒がしく鳴いたので、声を潰しました。
後処理が悪かったのか、半身が動かなくなりました。
動く部分を振り回して、閉じ込めた押し入れの中暴れまわるので片腕を折ったら、やっと大人しくなりました。
最近ご飯を食べてくれません。
無理矢理口に入れても吐き出すので、しょうがないので血液から食事を取らせます。
話しかけてもこちらを向いてくれません。
何故でしょうか。僕は自分だけの君が欲しかったのに。
無理矢理こちらを向かせれば、君は音のない声で「しにたい」と言いました。
勿論、そんな願いを叶えてやれるわけがありません。
「他にはないの」と聞けば、君は黙ってしまいます。
そんなやり取りが、毎日行われ、それが僕と君の唯一の会話でした。
ある日、君は何故かいつもよりご機嫌でした。
何もしなくてもこちらを向いた君は、動く片腕で僕の手のひらに文字を書きました。
『てがみがかきたい』
「誰に?」と聞けばゆっくり人差し指を上げて僕を指しました。
君から手紙を貰うなんて、ちょっと怖かったけれど、嬉しい気持ちの方が勝りました。
それに、やっと叶えてやれる願い事を言ってくれて、僕はウキウキしながら君に紙と鉛筆を渡しました。
受け取った君は貰ったものを良く眺めた後、書いてるところは見ちゃだめ、と押し入れの扉を閉めてしまいました。
扉は案外すぐ開きました。
押し入れの隙間から君が差し出したのは、紙じゃなくて先っちょの折れた鉛筆。
僕は笑ってしまいました。「削ってきてあげる」と鉛筆を受け取る時、キミも笑っていることに気付きました。
君の笑顔を見たのは、何か月ぶりだろう。
なんだか無性にうれしくて、僕は鼻歌なんて歌いながら鉛筆を削りました。
「はい」と鉛筆を差し出せば、君は相変わらず音のない声で「ありがとう」と言いました。
今日は何ていい日だろう。
君といっぱいおしゃべりが出来るし、手紙だってもらえてしまう。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・手紙?
がたがたと再び閉まる押し入れの扉を眺めながら、僕は思いました。
暗闇の中で手紙なんて書けるのだろうか?
押し入れの取っ手に手をかけたところで、中から小さく「ぶしゅ」という音が聞こえました。
僕は、押し入れを開けませんでした。
銀時は万事屋を飛び出して、方向も分からずただただがむしゃらに走り続けた。
壊してしまった。殺してしまった。俺が。
ふと前を見ると、顔面蒼白な山崎が立っていた。
その後ろには土方、総悟もいる。どちらも額に冷や汗をびっしょりかいていた。
「旦那も、見たんですか」
「え」
「俺たち全員、アイツが死ぬ夢を見たんだよ」
夢・・・?
そんなはずはない。
小さいのにやけに響いた刺突音が、今も耳に残っている。
「・・俺のは・・・夢じゃないかもしんね・・」
「旦那?」
銀時は3人と共に再び万事屋へと戻った。
夢ならばそれでいいのだ。ただ、夢じゃなかった場合。
大人しく出頭しようと思う。例えその場で斬り捨てられようとも、それが報いだと思った。
重苦しく開けられた寝室の扉の向こうを見て、銀時は死にたくなった。
一番奥、窓側の押し入れがほんの少しだけ開いていて、その側には一枚の ――――
――― 先程自分がに渡したものと同じ便箋が、4つに畳まれて転がっていた。
斬り捨て必須。
しかし自分にはこのメッセージを読む義務が残っている。
自分が追い詰めて殺してしまった。そんなが最後に伝えたかった事。
土方らにも促され、銀時は大きく息を吸って拾い上げた便箋を広げ、
書かれていた内容を読み上げた。
「最後に、もういちど・・・・
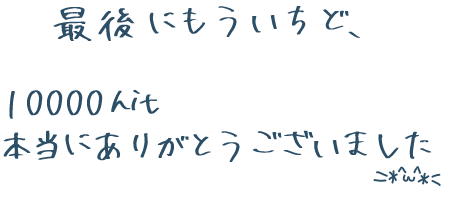
「・・・・ってどんなオチぃぃいいいいいい?!!」
銀時の叫び声とともに、ぐしゃぐしゃに丸められた便箋が床に叩きつけられた。
ここまでご覧頂いてありがとうございました。
これからもよろしくお願いいたします。
11/11/9 ねこえんじゅ=*^ω^*=
back