どうも屯所内が浮ついている。
一か月程の潜入捜査を終え久々に屯所に戻ってきた山崎退は、屯所内の雰囲気についてそんな印象を受けた。屯所内ですれ違う隊士の皆が皆、そわそわと忙しないのだ。便所の鏡の前で身だしなみを確認する隊士をやたら見かけた気がするし、やたら外回りに出たがる隊士の多い事多い事。せっかく戻って来たというのにこれでは落ち着けやしない。
それにしても、いったい何があるというのだろうか。
山崎の疑問の答えは、思わぬところからもたらされた。
「何してんの?さん」
人目を憚るように辺りを見渡しながら台所の裏口に立っている人物。それがよく見知った人物――真選組の紅一点、である事に気づき、山崎は声を掛けた。
も真選組の隊士なのだから、屯所の台所に立ち入ろうとするのに何ら不思議はない。
不思議なのは、“人目を憚るように”台所に入ろうとしている点だ。
案の定、は山崎の存在に気づいていなかったらしく大げさに驚き、その拍子に抱えていた紙袋を落っことした。
その紙袋からわずかにはみ出たモノが、目に入る。
「……見た?」
「……うん、なんていうか、ごめん」
――ああ、どーりで野郎どもがざわついているわけだ。
紙袋からはみ出たレシピ本の題名『手作りお菓子レシピ〜バレンタイン特集〜』を見て、山崎はどこか他人事のようにそんな感想を抱いた。
「にしてもちょっと意外だな。さんこういうイベント苦手とか言ってなかったっけ」
「……苦手だよ。ってかこんなのガラじゃないって事は自分でものたうちまわりたい位自覚してるよ。退くんも似合わないとか思ってるでしょ」
「いや俺そこまで言ってないけど。なんでそんな常になく卑屈なの」
レシピ本をぱらぱらと捲りながら、山崎は呆れの溜め息をついた。対するは気まずそうに山崎から顔を背けている。そんなの様子にまたひとつ溜息が零れた。食堂の解放時間を過ぎているために台所も他に人気もなく静かなもので、その溜息の音は思いの外響いた。
「まあ、万事屋の旦那は甘いの全般好きみたいだしなんでも喜ぶんじゃないかな」
「なんかそのなんでもいいってのがまた難し……ちょっと待って。なんでそこで当然のごとく銀さんなの」
「なんでって……クリスマスに旦那に連れてかれてたって屯所内で結構広まってるけど。沖田隊長も肯定してたし。ものすごく楽しげな顔で」
「……あんの腹黒ドS上司ィィィィイ!!」
確かに噂話を肯定した時の沖田の楽しげな顔は爽やかに黒かった。部下をいじる格好のネタというワケか。がこの噂を今まで知らなかったあたり、噂が届かないよう手を回していたかも知れない。あとで自分がそのネタでをからかう為に。だとしたらそこまでする周到さには思わず感服する。ってあれ、じゃあ今ここで彼女にその噂を伝えたらマズかったのかな。主に俺の身が。
一抹の不安が過ったが今考えても詮無い事だと思考を切り替え、もう一度レシピ本に視線を落とす。
ガラではない、と本人が言うように確かにとバレンタインという組み合わせはあまり結びつかない。何せ義理でもいいからくれとせがむ隊士を一刀両断(侮る事なかれ、彼女は正に文字通り、そんな軟弱なことを言う精神を叩き直してやるとせがんできた隊士を稽古で叩きのめしたという実績持ちだ)するような女性だ。誰でも意外に感じるだろう。
ただし、意外には思うが別に似合わないとまでは思わない。少なくとも山崎にしてみれば。
「……随分とまあ、いじらしい事で」
惚れた男の為に菓子を作る。なんとも微笑ましく、健気で可愛らしい一面だと思う。
そうは思うのだが、
――なんか、面白くない。
心になんとも言い表しがたい靄が広がる。
不思議そうに此方を見つめるに気付いて、山崎は我に返った。
――いやちょっと待て。なんで、何が面白くないの俺。
自分で自分の思考に思わずつっ込む。自分は今何を考えた。
内心激しく首を振って思考を否定したいところだが、の手前首を振るのは堪えた。
深く、考えてはいけない。そんな気がする。
「退くん?どうかした?」
「あー……いや、なんでもない。それよりさん、失礼を承知で聞くけどさ……お菓子、作ったことあるの?」
「……レシピ本用意してる時点で察してよ」
「……ないんだね」
予想はしていたがなんともはや、勇敢というべきか無謀というべきか。いや、レシピを用意しているだけまだ慎重と言える……のだろうか。何せ男所帯での生活が長いせいか、の手料理はかなり豪快だ。カレーひとつとってみても、丸ごと入っているのかのような具のでかさにいつも驚かされる。(まあ、慣れればアレはアレで味がある、とは思う)。
だが、普通の料理と違って菓子作りは繊細さを要求されることが多い。材料を取り分ける段階でほんの僅かの数量を間違えるだけでも、成功と失敗の明暗がはっきり分かれる。
も自分の料理の腕は自覚しているようだが、さてどうするのだろう。うなだれている様子を山崎が見つめていると、はおもむろに顔を上げた。
「退くん、こうなったら乗りかかった舟ってことでひとつお願いがあるんだけど」
「……何かな、さん」
――あ、なんか嫌な予感がする。
「手伝ってくれないかな、お菓子作り」
――ああ、そうくるのか。やっぱり。
「……いや、いいの?俺が手伝っても」
「何言ってるの。むしろ退くんにしか頼めないよ」
むしろこっちが何言ってるのって言いたい。
今度は山崎がうなだれる番だった。何この人、無自覚怖い、天然怖い。
それでも、不安気に見上げてくるの目を見れば否と言えない辺り、自分も大概甘いよなあ、と山崎は内心で自嘲した。
手伝う、といっても山崎自身菓子作りが得意というワケではない。
なので何をすればいいのだろうかと少し身構えたが、実際頼まれたことはレシピ本を参考にの手順が合っているか確認してほしいというものだった。
「……まあ、そりゃそうだよな」
「ん?何か言った?」
さすがに他の男にチョコ作りそのものを手伝わせたりはしないか。山崎はなんでもないと首を振って誤魔化した。
ちなみに作る菓子はブラウニーにした。レシピ本の中で比較的容易に出来そうだというのが大きな理由なのは、まあ今までのやり取りからして言わずもがな、だ。
は若干おぼつかない手つきで材料をかき混ぜている。その表情はとても真剣で、それを見つめる山崎の胸に、また靄がかかる。
本当は、この靄の正体に察しはついている。気付かないほど鈍くもないし、子どもでもない。
そして、気付かない振りをしてやり過ごす術を知っている程度には、大人である自覚もある。
――だって、不毛すぎるよなあ。いくらなんでも。
他の男の為に尽くす彼女の真剣な表情に惹かれるとか、不毛すぎていっそ喜劇だ。そう思わなければやってられない。
今はが幸せであるのなら、と素直に祝福する気持ちの方が大きい。それが此方にとって幸であるのか不幸であるのかはわからないが。ともかく、今ならまだ間に合う。今はまだ小さい醜い感情をこれ以上育てないよう、蓋をすべきだ。
「――よし。こんなぐらいでいいかな、退くん」
「うん、いいんじゃないかな。もう後は型に流しこんで焼くだけみたいだよ」
感情を殺す術を否が応にも得る職種である事を、感謝するのは初めてかもしれない。それもこんな形で。
きっとは山崎が今何を考えているのか、気付いていない。それでいいんだと、山崎は自分に言い聞かせた。
オーブンが軽やかな電子音で加熱完了を告げる。料理好きな隊士の執念、もとい要望で最近導入されたオーブンだが、時間設定して開始ボタンを押すだけとか、最近の家電の発展ぶりには驚かされる。
が緊張した面持ちでオーブンから焼き上がったブラウニーを取りだす。見たところ、ブラウニーに焦げたり、萎んだまま等、変なところは見受けられない。
「……出来た。出来たよ、退くん」
「……ああ、うん。よかったよ、上手くいったみたいで」
最初はどうなる事かと思ったけれど。最後の一言は感動に水を差してしまいそうだったので呑みこんだ。だってチョコを溶かすと聞いてそのままお湯につけようとするなんてベタな事、まさかする人が居るとは思わなかった。いや志村の姐さんなら或いはと思わなくもないが、あの人はなんでも暗黒物質に変化させる規格外だ。比べるのは失礼だろう。……どちらに対してかは、あえてノーコメントでお願いしたい。
外見上に問題は見受けられない。となれば次に確認しなければならないのは、味だ。
はブラウニーを切り分けた。そのまま自分で味見をするのだろうと山崎は思っていたから、次のの行動には面食らった。
「はい、退くん」
「……え?」
目の前に差しだされたブラウニーと、を思わず交互に見比べた。は期待の眼差しで此方を見つめている。しかも小首を傾げながらとか、あざといにも程がある。あざといのは本人無意識なんだろうけど。そんなのわかっちゃいるけども。
「……いや、いいの?貰っても」
「何言ってるの。元々退くんの分も考えて多目に作ってたんだよ。ほら、バタバタして皆忘れてるみたいだけど、退くんこないだ誕生日だったでしょ。それに今日のお礼もあるしね」
まあいろいろいっしょくたにしちゃって申し訳ないけどさ。
照れくさそうに笑うを見て、山崎は今日かつてない脱力感に襲われた。
確かに気付かなければいいと思った。気付かれて困るのはお互い様だ。だがこの現状はあんまりではないだろうか。
――人の気も知らないで。
そこからの行動は半ば衝動に突き動かされていた。
の手を取り、持っていたブラウニーを口に運ぶ。固まったにはあえて気付かない振りをして、そのまま咀嚼した。
「うん、味もちょっと甘めみたいだけど、問題ないと思うよ」
「え、あ、ああ、そう?なら、よかった、かな」
「ちなみに気持ちは有り難いけどさ、俺はこのひと切れで充分。あとは旦那にあげなよ」
ごちそうさま、とそこで会話を打ち切って、山崎は台所を後にした。これ以上一緒にいたら、何をしでかすか自分でもわからない。少し頭を冷やそう。
満足、すべきなんだ。出来たてのひと切れをくれただけで、ほんの少し気にかけてくれているだけで、満足すべきなんだ。山崎は必死に自分に言い聞かせる。
言い聞かせて抑えられるほど、甘くないのは重々承知だ。
「……甘」
口に残るブラウニーは、甘いのにどこかほろ苦かった。
ほろ苦ブラウニー
back
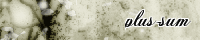 plus-sum 月葉さんありがとうございます*^^*
plus-sum 月葉さんありがとうございます*^^*